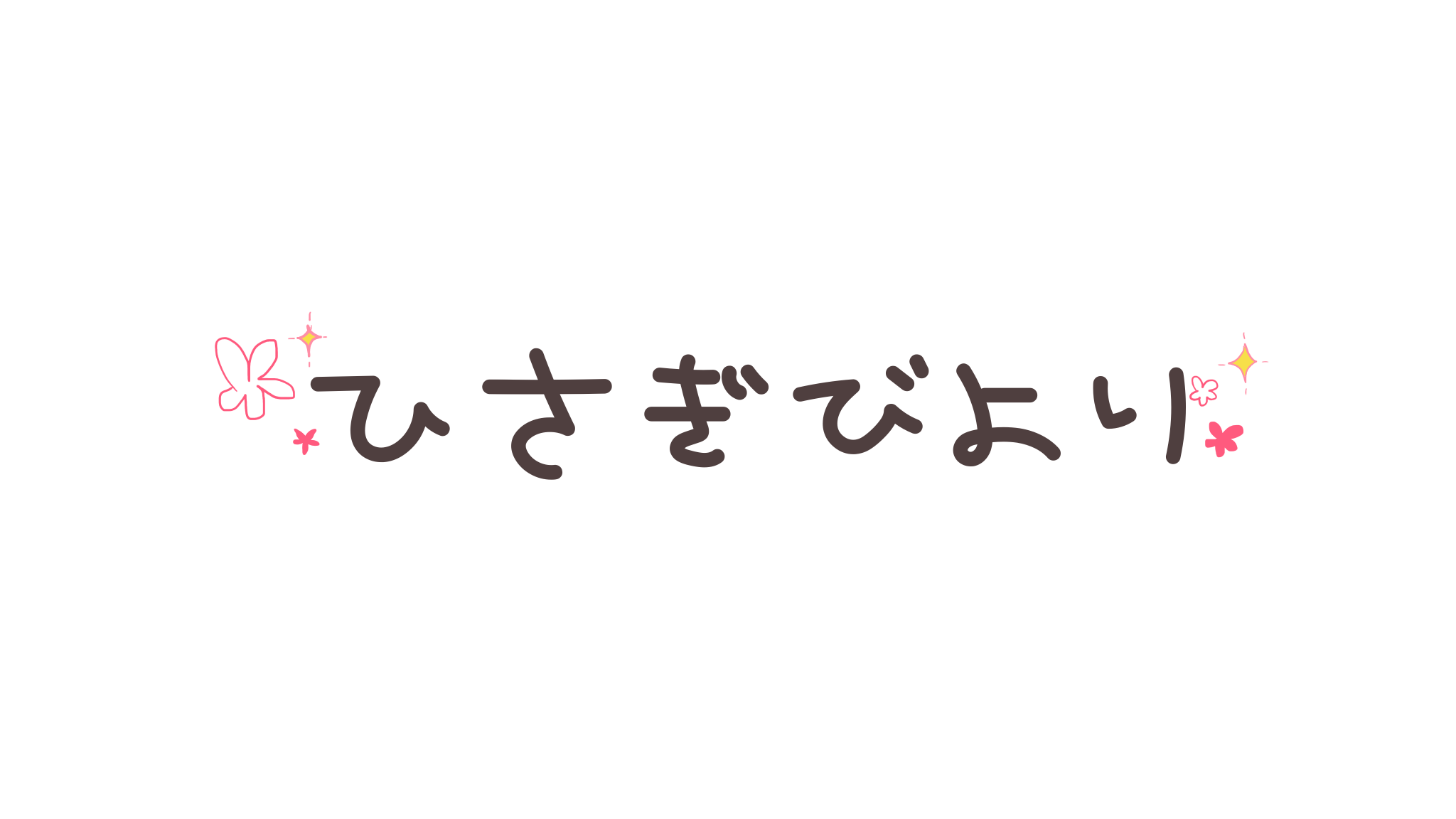「香月さん、ちょっと待って!」
「えっ!?どうかしましたか、藁太郎さん?」
少し大きな声になってしまい、香月さんは驚いて振り返る。僕はさっき香月さんが言っていた言葉を思い出しながら彼女に伝える。
「えっと……、それ激辛じゃないんだけど、とうがらし入りで少し辛いやつなんだ……。」
「えっ?……あっ!ほんとです。文字が小さくて気付きませんでした……!」
香月さんは小走りで持っていたカップ焼きそばを棚に戻した。
「……あぶなかったのです。藁太郎さん、教えてくださってありがとうございます。とても助かりました。」
「そ、そんな大したことはしてないけど……。でも香月さんが大変な目に合わなくてよかったよ。」
喉に優しくない、と言っていたことを何故か急に思い出し、気にするくらい喉が大事なのだろうと思い香月さんを引き留めた。ただそれだけのことだったが、ここまで感謝されるとは思っておらず僕は少々戸惑ってしまう。
香月さんは再び棚の前に戻り、カップ焼きそばのコーナーを見つめだす。
……と思いきや、不意に僕の方を見る。
「……それ、美味しいんですか?」
「え?」
突然尋ねられたので僕は少し裏返った声で返事をしてしまった。香月さんの視線は僕が持っているカップ焼きそばに向けられている。
「あ……ああ、これ?美味しいよ。色々食べたけどこれが気に入ったんだ。」
香月さんは少し考える素振りを見せながら……というか、顎に少し丸めた手を当てて思いっきり考えながらカップ焼きそばを見つめている。
そして考えが出たのか両手の指先をトン、と合わせ
「私もそれにします!」
と、満足した微笑みをこちらにむけ、『甘口ソース』と書かれたカップ焼きそばを棚から取り出しレジへと向かう。
……さすがは学園での有名な美少女というべきか、かなり明るいはずの店内にさらに大きな光が現れたかのような笑顔だった。
なんというか、ズルい人だと思ってしまった。一体何人があの笑顔に魅了されてきたのだろうか……。『罪な人』とも表せるのだろうか、などと考えていると会計を終えた香月さんがこちらに近づいてきた。
2人とも会計を終え、明るい店内から暗い外へと出ていく。こちらの景色の方が幾分か目に優しい気がする。
ふと、僕は香月さんの帰りの道中が気になり尋ねる。
「そういえば香月さん、帰りは1人で帰るの?」
「いえ、おうちの人が近くで待っていてくれているのです。夜道は危ないですから。」
こちらの意図を汲み取ったのか、香月さんは1人で帰るわけではないことを僕に教えてくれた。
すると、少し遠くから「ひさぎちゃーん」と呼ぶ声が聞こえた。香月さんはそれに反応し、僕に言葉を続ける。
「あ、おかあさんが呼んでるのです。では藁太郎さん、また明日、なのです。」
『ああ、また明日』と伝えようとしたが、香月さんはそのまま少し小さな声で僕にささやいた。
「……これで私たちは『共犯者』、なのですよ」
そう伝えると、香月さんは声のした方へと駆けて行った。
僕に『共犯者』と告げた香月さんは、いたずらをしている子どものようにニヤリと笑っていた。
いつもは眠たげでスッキリと起きている姿を見たことは無い。そもそも学校ではいつもぼんやりとした表情しか見たことがなかった。
しかし、今は。
「……ズルい。」
そう、口から自然と言葉が漏れていた。
帰路に就き自宅を目指す。玄関の扉を開け、台所でお湯を用意し、一通りの作業を終えてカップ焼きそばができた。
漂ってくるいつもの香りを楽しみながらやっぱりこの味が1番だなと思い、同じカップ焼きそばを買っていった香月さんのことを思い出す。
「やっぱり『罪の味です!』とか言ってるのかな。」
普段の彼女の性格を思い出しながら、先程のあどけない表情も同時に思い出した。
「……どっちが罪なんだか。」
そうつぶやいて、カップ焼きそばをひと口食べる。
……が、すぐに口の中の違和感に気づき咳き込む。
「ゲホッ、エホッ……、なん、辛ぁ……!?」
僕は急いでカップ焼きそばのフタを見る。そこには『激辛ソース』の文字。
慣れているからとよく見ずに取ってしまったからか、『彼女』のあの表情を独り占めしたからか、僕への制裁か何かが降りてきたのだろうか。痛いのか辛いのかわからないが、ただひとつ言えるのは
「罪の味、だ……。」
大好きだったあの味が間抜けにもほどがある手違いにより強烈な味覚への攻撃に変わり果て、僕の両目は涙目になり、辛さで痛めた喉からガラガラになってしまった声が漏れ出てきた。
その日の夜の出来事は全て『激辛ソース』に塗りつぶされ、次の日の朝まで僕の喉はヒリヒリと痛かった。
2020/10/28 擱筆 2020/11/07 連載終了