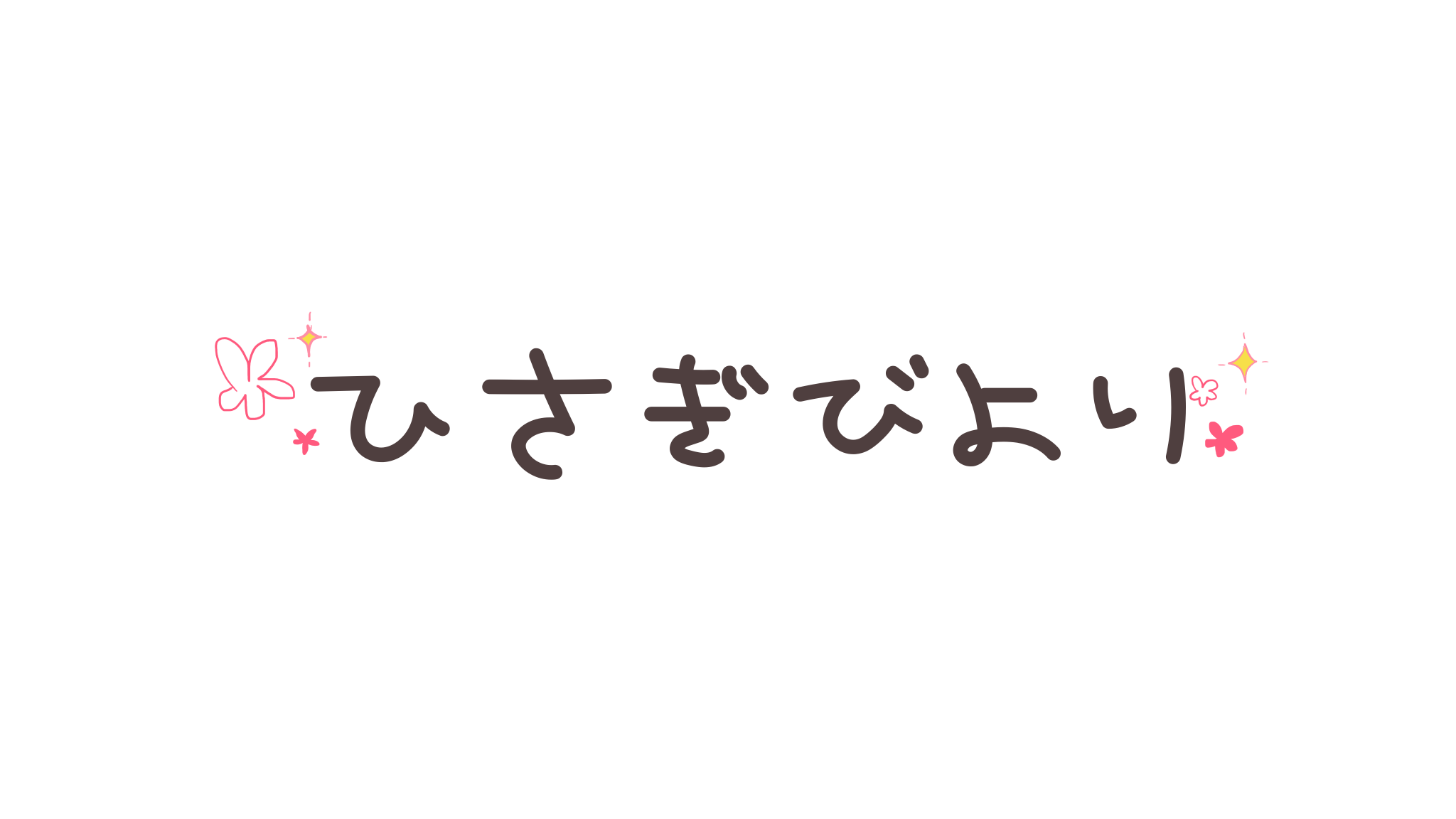春うららというべきか、雨で花は半分ほど散ってしまったが、涼しい風が流れていく。晴天、散歩日和。いろいろな言い方があるだろう。
…しかし、彼女にとってこのシチュエーションを表す言葉は一つしかない。
「お昼寝日和です…ふあぁ」
「香月さん…こんなところで寝てたの?」
彼女は香月ひさぎさん。僕は香月さんと呼んでいる。成績優秀、才色兼備。どこをとっても完璧としか言いようがない少女だ。
言いようがない、が。
「…すぅ」
昼休み。中庭の花に水をあげる当番だった僕は、ベンチで寝ている彼女を偶然にも見つけてしまった。
…こんなところに来てまでわざわざ眠るのか。と、心の中で突っ込みを入れる。
それとも、香月さんにとってここは憩いの場所なのだろうか。確かに人気がないから絶好のスポットといえばそうなのかもしれない。
文武両道である彼女の唯一のおかしなところというか…個性といえるところは、このようにいつも眠たげで日中寝ているところだ。
「…ってちょっと、香月さん!昼休み終わっちゃうよ!」
「んん…こうたろうさん…お姫様抱っこなのです…私はおひめさまですから…わたし…」
「なっ…!?」
彼女はお姫様抱っこでの移動を所望のようだ。いや寝言だろう。多分。おそらく。きっと。
彼女が僕の名前、菊麦藁太郎(きくむぎこうたろう)のことを呼びだしたので、僕はひどく狼狽える。僕にしろという事だろうか、いや違う、いやでも夢の中に僕がいるという事は…、いや、偶然だ、きっと僕のことじゃない。いややっぱりでも…。
「…さん、…藁太郎さんっ」
僕が考えているとき、突然明瞭な、しかし少しハスキーな声が降ってきた。
「早く帰らないと授業に遅れちゃいますよー。」
…いつの間にか彼女は起き上がり、ピンク色の髪を整えていた。
「…。」
唖然としている僕をよそに、そのまま彼女は教室まで走り出した。
…いや、別に期待なんてしていない。彼女の不思議な発言や寝言は今に始まったことではないのだから。
女の子を抱き上げることなんか気にしていない。やってみたかったなどとは思っていない。決して、期待をしていたわけではない。うん、それでいい。そうだぞ、藁太郎。
僕は僕自身に言い聞かせ、彼女の後を追うように教室まで走り出した。